3人に1人が認知症になる時代がやってくる
約3人に1人が認知症になる可能性も
最近、人との約束を忘れたり、手袋や傘や帽子などが見つからなかったりすると、私はしばしパニックに陥る。本書執筆時点で70歳になったところで、こうした出来事は避けられない老化の兆候のように思えるからだ。とはいえ20代になったばかりの頃も、友人を夕食に招いておきながらすっかり忘れ、彼が家に来たときは留守にしていたということがあった。その数年後、転居する私の送別会を隣人が企画してくれたのに、仕事に気をとられてすっぽかしたこともあった。そして人生を通じて、いろいろなモノを失くすことで有名だった。そんなことを思い出すと、また元気を取り戻す。
ただ、私が不吉な予感にとらわれるのにはもっともな理由がある。神経変性疾患にかかり、物忘れどころか、自分が何者であるかさえまったくわからなくなってしまうリスクは誰にでもある。
今日、認知症の患者数は5000万人を超える(*1)。世界のほぼすべての国で高齢化が進むなか、その数は2030年には7800万人、そして2050年には1億3900万人に達すると予想される。イギリスのイングランドとウェールズでは最近、主な死因として認知症が心疾患を上回った(*2)。心疾患の治療法は大幅に進歩してきたにもかかわらず、認知症には依然として有効な治療法が存在しないことも一因だ。アメリカでは依然として心疾患、癌(がん)、事故など従来型の死因を下回っているものの、認知症で死亡する人の割合は徐々に高まっている。2015年に生まれた人のほぼ3分の1は、何らかのタイプの認知症を患うと推定されている(*3)。
認知症患者の半分以上を占めるのがアルツハイマー病だ(*4)。1900年頃、当時まだ名前もなかったこの病気の発病の兆候を指摘した、ドイツの精神科医アロイス・アルツハイマーにちなんで命名された。患者は落ち着いて明晰な時期と、ありふれたモノや自分の置かれた状況がわからなくなり、物忘れをし、動揺したり、ときには錯乱したりする時期を行き来する、とアルツハイマーは書いている。
それはほんの始まりに過ぎない。病気が進行すると、アルツハイマー病患者の多くは家族や友人も認識できなくなる。話す、食べる、飲むといった基本的活動にも支障をきたす。自分を制御できなくなり、自分が誰だかわからなくなり、自らをとりまく世界を理解できなくなっていくことに次第に恐怖を感じるようになる。夫や妻、祖父母、大切な友人である患者の人格が失われていくのを見なければならない周囲の人々はさらにつらい思いをする。
認知症につながるタンパク質の欠陥
アルツハイマー博士が病気を指摘してから1世紀以上たった今、アルツハイマー病の生物学的背景の理解は大きく進んだ。パーキンソン病、ピック病など他の神経変性疾患についても同様だ。そのすべてには2つの共通点がある。1つは年齢とともに発症率が上昇すること、そしてもう1つは原因がタンパク質の機能不全であることだ。
すでに見てきたように、タンパク質はアミノ酸の長い連鎖で、生成される過程で奇跡のように折り畳まれていく。いや、奇跡という言い方は妥当ではない。タンパク質が折り畳まれる理由は、アミノ酸のなかには油のように疎水性、すなわち水にさらされるのを嫌うものがあるからだ。反対に親水性のアミノ酸は水分子と触れ合うのを喜ぶ。
タンパク質鎖が作られる過程で、疎水性のアミノ酸の大半がタンパク質の内側に、親水性のアミノ酸が周囲を囲む水と触れ合うように外側にむき出しになるように折り畳まれることで、特徴的な形に折り畳まれていく。ほとんどのタンパク質鎖には安定し、機能を発揮するための特定の形や折り畳み方がある。ときには1つのタンパク質鎖が他の鎖とともに畳まれ、複数の鎖から成る複雑な形になることもある。ただ原則は変わらない。
私たちの細胞の1つひとつは驚くべき調整力を発揮しながら、必要なときに必要な量のタンパク質を何千個と作る。そのすべてが完璧に調和した1つの集合体として機能しなければならない。だがもちろん、このプロセスがうまく働かなくなることもある。
家財や家庭用品がさまざまな理由から不要になるケースを考えてみよう。新品の道具でも製造ミスによってさまざまな欠陥がある状態で出荷されてくることもある。道具を使っているときにうっかり壊してしまうこともある。あるいは徐々にすり減ったり錆(さ)びたりして、危なくて使えなくなったり完全に使えなくなったりする。あるいはかつては必要不可欠であったものの、もう必要がなくなったという製品もある。子供が成長したら哺乳瓶やベビーベッドは不要になる。技術が変化することもある。カセットレコーダーやフィルム式カメラはもはや無用の長物だ。持っている服が時代遅れになったり、もう着たいと思わなくなったりする。食べ物の賞味期限はもっと短い。
私たちは日々の生活のなかで、当たり前のようにこうしたことに対処していく。食べ残した食品が腐ったら捨てるし、洋服が古くなったら修繕したり捨てたりするし、壊れた電子機器は修理したり廃棄したりする。そうしなければ家の中がすぐにガラクタでいっぱいになり、住めなくなってしまう。
細胞やそこで作られるタンパク質についても同じことが言える。タンパク質にも製造欠陥は生じうる。タンパク質鎖の組成が不正確だったり不完全だったりすることもある。適切な形に折り畳まれないこともある。存在しているあいだに折り畳みが崩れたり、化学物質その他の作用因子によって損傷を受けたりすることもある。私たちが特定のアイテムを人生の特定の時期にしか必要としないように、多くのタンパク質は細胞が成長する特定の段階、あるいは何らかの環境的刺激に対応するあいだなど、ほんのわずかな期間だけ必要とされる。
そして私たちが欠陥のある製品、使い古した製品、損傷した製品を捨てたりリサイクルしたりするのと同じように、細胞ももともと欠陥のあるタンパク質や変形したタンパク質を発見し、破壊する方法を進化させてきた。また完璧に正常でも、必要のなくなったタンパク質を廃棄する方法もある。いずれのケースでも細胞は、問題のあるタンパク質をその構成要素であるアミノ酸に分解する。分解されたアミノ酸は新しいタンパク質やエネルギーを生み出すのに使われる。
しかし細胞内のタンパク質と家財や家庭用品には重要な違いがある。メーカーはふつう、製品を販売してしまえばあとはどうなろうと気にしない(保証期間中は別だが)。しかもあなたの家の洗濯機のメーカーは、洗濯機と他の家電との互換性を持たせる必要はないので、あなたが所有する冷蔵庫や電子レンジのブランドが何か、そもそもあなたが冷蔵庫やレンジを持っているかどうかなど気にしない。一方、細胞はタンパク質を製造するだけでなく使用するので、何千というタンパク質がすべて問題なく協調的に働くように目配りしなければならない。
欠陥の防止機能と加齢による機能低下
年齢を重ねると、細胞の品質管理やリサイクルの仕組みが劣化し、神経変性疾患だけでなく炎症、変形性関節症、癌など加齢に伴うさまざまな疾患につながっていく。このため細胞はタンパク質の集合体の品質と健全性を確保するため、たくさんの方法を編み出してきた。
タンパク質の欠陥にはさまざまなものがある。タンパク質鎖は私が過去45年にわたって研究対象としてきた大きな分子機械であるリボソーム上で生まれる。リボソームはmRNAに書かれた遺伝情報を読み、タンパク質鎖を作るためにアミノ酸を正しい順番でつないでいく。このプロセスは数十億年かけてかなりの完成度に進化してきたが、それでもときには欠陥製品を生み出す。mRNAに間違いが含まれていることもあれば、リボソームが読み間違いをすることもある。そういうケースでは新たに作られたタンパク質にはアミノ酸が誤った配列で並ぶことになり、機能不全を起こす。新品の電子機器に不良品があるようなものだ。最近では私や同業研究者の多くが、細胞がこうしたミスを認識し、除去の対象とするメカニズムの解明に努めている。
リボソームのトンネルから出てきたタンパク質鎖のアミノ酸配列が正しくても、次は正しい形に折り畳まれるかという挑戦が待ち受けている。タンパク質鎖には正しい形を形成するのに必要な情報はすべて含まれているが、だからといって自然にうまくいくわけではない。大型のタンパク質の場合、折り畳まれていくあいだに疎水性の部分が他の部分とくっつかないように隔てておくのは難しい(同時に作られる別のタンパク質鎖とくっついてしまうのはさらにまずい)。
折り畳みプロセスの失敗にはたくさんのパターンがあるので(*5)、細菌から人間までのあらゆる生物の細胞は他のタンパク質が正しく折り畳まれるのを支援する特別なタンパク質を進化させてきた。私と同じケンブリッジ大学の科学者ロン・ラスキーは、ユーモアを込めてこの特別なタンパク質を「シャペロン」と名づけた(ラスキーはフォーク歌手の顔を持ち、科学者の生活をテーマにしてウィットに富む曲を自作してレコーディングまでしている。その1つが若い頃、イングランドの小さな会場で当時無名だったポール・サイモンと共演し、即座に自分は科学者の道に進んだほうがよさそうだと悟った経験を歌ったものだ)。ヴィクトリア朝の男女交際でお目付け役を果たした介添人(シャペロン)のように、〝シャペロン〞タンパク質もタンパク質鎖あるいは異なるタンパク質鎖同士の不適切な交流を防ぐ役割を担っている。それでもときにはタンパク質鎖の折り畳みの間違いは起こる。
タンパク質が正しい形に折り畳まれた後でもほどけることはある。鶏卵のタンパク質は一致団結して、受精卵をひよこに育てるという役割を遂行しようとする。だが私たちが鶏卵を茹(ゆ)でれば、タンパク質はすべて分解される。同じように牛乳にレモン果汁を入れて混ぜると、酸によって牛乳のタンパク質はほどける。いずれのケースでもタンパク質鎖がほどけると、タンパク質の内部にいた水を嫌う疎水性アミノ酸が周囲の水に触れる。それによってタンパク質は互いにひっついたり、絡まったりして、卵や牛乳はゲル状の固体になる。
茹でたりレモン果汁を加えたりしなくても、そもそもタンパク質は岩のような安定したかたまりではない。タンパク質内のアミノ酸は常にゆらゆらと揺れ、タンパク質自体も正常な形をとりつつ呼吸したり振動したりする。時間の経過とともに自然に、あるいは環境的ストレスに反応してほどけることもある。たいていは再び元の形に折り畳まれるが、ときにはそうならずに凝集することもある。私たちが歳をとるにつれてより多くの凝集が起き、それはより多くのタンパク質が機能を失ったことを意味する。それ以上に深刻なのは、タンパク質のかたまり自体が認知症などの疾患につながる可能性もあることだ。

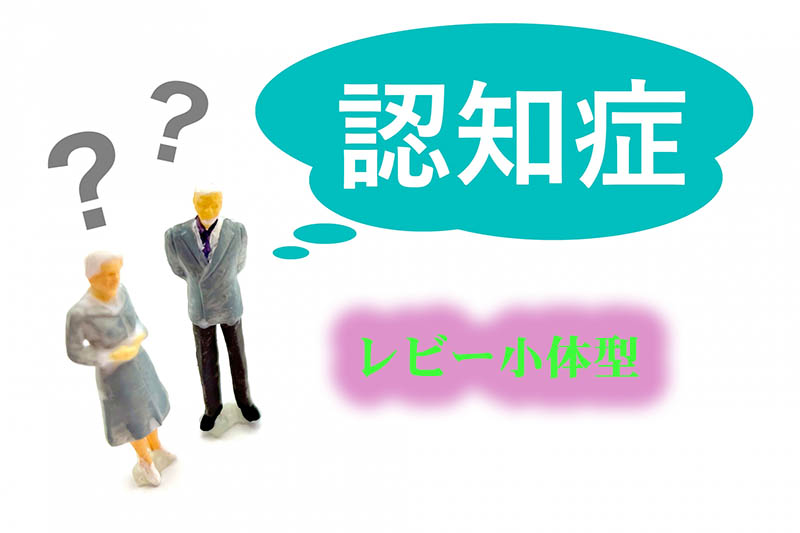


コメント