地元の医者にウソつかれてた! 「これからは毎月来るように」 年間自己負担額が4.7倍に
収益悪化から抜け出すための医院の方策で患者の為でない。
医師サイトに掲載されていた医療ニュースをシェア。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
地元の医者にウソつかれてた!診療報酬改定装い 「これからは毎月来るように」 年間自己負担額が4.7倍に
2025年11月04日 06時00分東京新聞
〈医療の値段 医師にたずねよう〉
2026年度の診療報酬改定の議論が本格化している。物価高騰などで、悪化する病院経営の立て直しが必要だが、医療費のムダを減らさないと保険料アップは避けられない。
高血圧や糖尿病など生活習慣病の過剰診療を見破り、医療費のムダをなくした患者家族の奮闘ぶりを報告する。(この連載は杉谷剛が担当します)
「これから3カ月分の処方箋は出せなくなる」
東京・多摩地区に住む木村麻里さん(仮名)は、近くの実家で1人暮らしする80代の父を連れて、地元の診療所に通っていた。
認知症の父には以前から高血圧・糖尿病・脂質異常症の三つの生活習慣病があり、3カ月おきに兄と交代で付き添った。
3疾患とも状態は安定していた。
「これから3カ月分の薬の処方箋は出せなくなるので、毎月来てもらうことになります」
2024年9月、木村さんは受付の女性にそう言われた。
「毎月は仕事を休めない」と困惑していると、院長から「土曜日仕事が休みなら、午前中にあなたが処方箋をもらいにくればいい」と言われた。
4680円→2万1960円「年金暮らしの父にはきつい」
窓口で支払いを済ませると、高くなったと感じたので、以前の診療明細書と見比べてみた。
半年前の同年3月の診療代は5870円。
父の自己負担は2割で、1170円を支払った。
ところが診療報酬が改定された同年6月の診療代は9150円、支払いは1830円と1.5倍に値上がりしていた。
改定前は3カ月に1回の通院だったので、年4回の診療代の父の負担分は計4680円だが、毎月通院するようになれば自己負担は1830円×12カ月=年2万1960円となり、1万7280円も高くなる。
「年金暮らしの父にはきついと思いました」と木村さん。
父に付き添った際、院内に「患者様への大切なお知らせ」という紙が張ってあるのに気付いた。
院長名で、次のような趣旨のことが書かれてあった。
「2024年6月に診療報酬が改定され、病気によって長期処方や検査が大幅に制限される。高血圧・糖尿病・脂質異常の3疾患は患者負担が変わる場合がある」
木村さんは「改定の影響で、父も毎月通院することになったのか」と思った。
調べたら、厚労省は長期&リフィル処方を推奨していた
だが、ネットで調べてみると「長期処方や検査が大幅に制限」というのはウソだと分かった。
実際はその逆で、厚生労働省は医療機関に対し、「患者の状態によって薬の長期処方や『リフィル処方』が可能」とする院内掲示を義務付けたのだった。
リフィル処方とは、疾患の状態が安定している患者に、薬局で3回まで使える処方箋を出すことだ。
2、3回目は診察を受けなくても薬を買うことができる。
患者は医療費が節約でき、通院に余裕ができる。
「国は患者のために長期処方やリフィル処方を勧めているのに、制限されたと書くのはひどい」。
木村さんはそう思い、兄に「やっていることがおかしいので、いろいろ確認しなければ」とLINE(ライン)で伝えた。
なぜ診療代が上がり、受診頻度が増えたのか。
自分で調べて医師に問いただすことにした。
頻回な日本の外来診療
経済協力開発機構(OECD)の2021年のデータで、日本の1人当たりの年間の外来受診回数は11.1回。
15.7回でトップの韓国に次いで多く、加盟38カ国中32カ国の平均6回の2倍近い「頻回」の状態だ。
日本は医療行為をすればするほど収益が上がる「出来高払い」のため、過剰診療や頻回診療を招きやすい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事に対する医師の意見を抜粋しました↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の1人当たりの年間の外来受診回数は11.1回と多いのは、他国よりも高齢者が多いのと、厚労省が診療報酬を安く抑えてるから、患者が気軽に医療機関を利用するからでしょう。
多くの医療機関が利益の為に診療をコントロールしているかのような印象操作はやめてほしい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
地元の医者が言う「処方箋が出せなくなる」というのは完全な誤りですが、1ヶ月毎の通院が望ましいのは確かです。
3ヶ月毎通院でかかりつけと言われても困ります。
高齢者の場合、1ヶ月でも状態が変わりますから1ヶ月に一回来れないなら近くの通いやすい診療所に転医することも考えるべきですね。
リフィルや長期処方は大きな病院では許されるかもしれませんが、最近の状態も把握せずに同じ処方を延々と処方できるわけがありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
80代で認知症、3つの生活習慣病があって3か月ごとの通院でよいという医者はかかりつけ医なら少ないのではないのでしょうか。
顔も忘れるし、何も聞かなくて良いから薬だけくれっていわれているようなものです。
そういう人はそれはそれでいても良いと思うのですが、開業医側からすると少なくともその人と真摯に向き合うことはなくなるでしょうね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
うちの診療所は自由診療なので保険診療のシステムについては知らないのですが、本当に必要な通院ならいいと思うのですが、無駄な通院であれば患者さんにとったら「騙された」となるでしょう。
一人当たりの1年間の外来受診回数が11回というのにも驚きました。
だってうちの診療所、ほとんどの患者さんが2回目の通院で完治終了し、そのあとは診察なしで薬だけもらうのOKにしてて、あとは年に1回のオシリ検診に来られているので、通院は多くて2回。
半数以上の患者さんが通院回数が年に1回です![]()
ただし肛門が狭くてブジー治療のために通院している患者さんは月に1回通院の人がおられます。
ブジー治療通院の患者さんも、肛門が拡がってくると通院の間隔があいていきます。
2ヶ月に1回になり、3ヶ月に1回になり、4ヶ月に1回になり・・・もう大丈夫![]() となれば治療を卒業し年に1回のオシリ検診の時だけブジーで広さを確認して拡げるという流れになっています。
となれば治療を卒業し年に1回のオシリ検診の時だけブジーで広さを確認して拡げるという流れになっています。
でもそう言えばあちこちの肛門科(を標榜する専門外のクリニック)から回って来た患者さんが、2週間に1回の通院を何年も続けていて、1年間で26回外来を受診。
トータルで払った医療費の金額は年間で薬代を合わせたら15万円超え。
「自由診療で高いと思ったけれど、結局2回目の通院で終わるのでトータルの金額で言うと先生の所の方が安いです」
と患者さんから言われたことがあります。
結局ね、保険診療って、腕が良くて一発で治した方が儲からなくて、ヤブで何度も何度も通わせる方が儲かる仕組み![]()
「いかにリピートさせるか」ということを考えるのが経営というもの。
うちの診療所は逆で「早く治して、いかに通院を終わらせるか」ということを常に意識して診療しています。
飲食店なら「美味しいからまた行こう」となるけれど、病院は逆でしょう?
できれば「行かないほうがいい所」です。
早く治して通院を終わらせようよと言いたい。
痔と違って高血圧、糖尿病、脂質異常症は「ずっと薬が必要な生活習慣病」なので通院もやむなしなのかもしれませんが、生活習慣を変えることなく、漫然と投薬治療だけ継続している状況は大凡、根本治療とは言えないのではないか。
本当にこの薬いるの![]()
という患者さんを見かけることもあるので、薬をもらうことが治療だと認識している患者側の意識も変えないといけませんし、薬を出すことが治療だと信じ切っている医師の意識変革も必要でしょうね。
いやー、なかなか難しい問題だと思います。
「病気は病院に行ったら医者が治してくれるもの」と認識している患者さんに、自分が引き起こした「病」について考え、原因を改めさせるには相当のエネルギーが必要ですから。
だから「医療のカタチ」って色々あっていいと思うんですよ。
保険診療は薬で治したい、薬が欲しいという患者さんが受診しているだろうし、うちみたいな変わった自由診療の病院には、そういう意識の人はほぼ来てないわけで、提供する医療も全く違えば、それを求める患者さんも違う。
それを患者さんが選べる日本の医療は、まだまだ海外に比べると自由度が高いと思います。
保険診療と自由診療の棲み分けがうまく行けば、どちらを提供するのか医師も選べるし、患者さんも選べばいいでしょう。
これから保険診療はどうなって行くのか関わりのない私には分かりません。
でも保険診療を外側から見ている人間として言いたいことはたくさんあります。
所詮、医療って仕事は人の不幸がメシの種。
病人を無くすことが究極の医療のゴールだと思うのですが、それが実現すると困るワケです。
病人があふれているほうが儲かる仕事。
なんだかなぁ・・・と思ってやってきましたが、幸い、肛門科って痔が治ったら通院が終わるのです。
だからこの仕事を続けていられるのかもしれません。
ある意味、幸せな診療科ですね。
痔でずっと通院している人に言いたい。
痔が治ったら通院は終わります。
だから早く治して通院を終わらせようよ。
(肛門が狭い人は頑張って下さいね![]() )
)

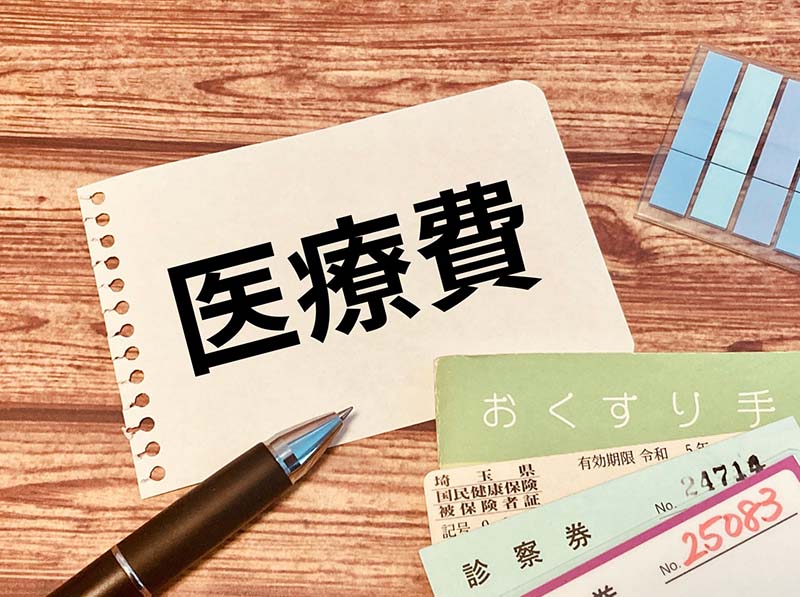



コメント