「宇宙が膨張してる」のではなく「物質世界が縮んでいる」とする新理論が発表――なんと観測データとも整合
観測の精度がどんどん上がるにつれて、このハッブル定数を求める方法によって「答えが少し違う」という問題が目立つようになってきました
私たちは学校で、「宇宙はビッグバンからずっと膨張しつづけている」と習います。
銀河どうしの距離はどんどん離れ、宇宙という“ゴム風船”がふくらんでいる、というイメージは、多くの人にとっておなじみの宇宙像になっています。
しかしアメリカのクエスト・サイエンス・センター(Quest Science Center)で行われた研究によって、「宇宙が膨張している」のではなく「物質世界が縮んでいる」という理論が数式化されました。
研究では、原子の大きさや時間の刻みなど、物質の世界のスケールだけがビッグバン当初から今までの期間に3〜4割ほど小さくなったとすると、最近の宇宙観測が突きつけているいくつかの謎――「ハッブル定数の問題」や「ダークエネルギーの変化の問題」――などが、ひとつの「縮む物質世界モデル」でまとめて説明できる可能性が示されています。
もし単なる理論の提示だけなら疑う人もいるかもしれません。
しかし今回の理論は観測データとの整合性もチェックされており、非常に魅力的と言えます。
もし本当に、広がっているのは宇宙空間そのものではなく、私たちの側の物差しと時計のほうだとしたら、私たちが見ている「膨張宇宙」はどんなふうに見直されることになるのでしょうか?
研究内容の詳細は2026年1月20日に『Preprints.org』にて発表されました。
観測精度が上がるほど見えてきた宇宙論のほころび
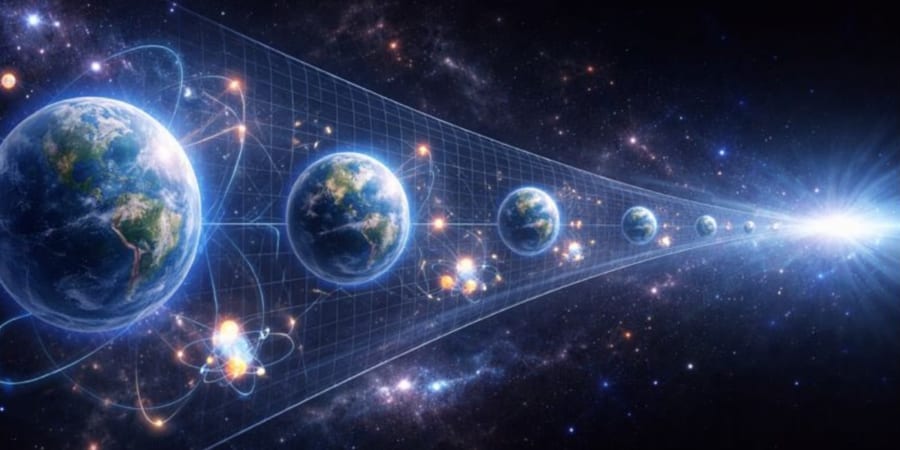
私たちが学校で習う宇宙の姿は、とてもシンプルです。
宇宙はビッグバンという超高温・超高密度の状態からスタートし、そのあとずっと膨張を続けている、と説明されます。
よく使われるたとえは「ゴム風船」です。
ゴム風船の表面にいくつか点を書き、風船をふくらませていくと、点と点の間の距離はどんどん大きくなっていきます。
点そのものは風船の表面を動いていないのに、風船が伸びることで、あたかも点同士が遠ざかっているように見えるわけです。
宇宙も同じで、「銀河が空間の中を飛んでいる」のではなく、「空間そのものが伸びている」と考えるのが、いまの主流の説明です。
宇宙が本当にどれくらいの速さでふくらんでいるのかを表すために、研究者たちは「ハッブル定数」という数値を使います。
ところが近年、観測の精度がどんどん上がるにつれて、このハッブル定数を求める方法によって「答えが少し違う」という問題が目立つようになってきました。
「昔の宇宙」を手がかりに求めた場合と、「今に近い宇宙」をもとに求めた場合で、はっきりとした食い違いが見つかってきたのです。
「宇宙背景放射」など大昔(初期宇宙)からハッブル定数を推定するとある値が出てきます。
一方で、私たちの近くにある銀河や超新星を直接観測して「今この瞬間の膨張のしかた」を測ると、そこから導かれるハッブル定数はそれより少し大きい値になります。
この食い違いは「ハッブル定数の緊張」と呼ばれ、ざっくり言えば一割ほどの差がありそうだと言われています。
「誤差の範囲」と片付けるには、そろそろ苦しくなってきたレベルのズレです。
似たようなズレは、宇宙の「ボコボコ具合」を表す指標でも見つかっています。
宇宙には銀河や銀河団、ダークマターがつくる巨大な泡構造など、さまざまなスケールの「かたまり」が存在します。
重力で物質がどれくらいまとまっているかを表す指標だと思ってください。
その「どれくらい凸凹しているか」をまとめた量のひとつが、S8(エスエイト)と呼ばれる指標です。
初期宇宙からの推定値と、現在の宇宙を重力レンズなどで直接測った値を比べると、やはり約1割の差があり、後者の方が小さいことがわかっています。
本来なら時間がたてばたつほど重力で物質は集まりやすくなるはずなのに、観測では「思ったほど集まっていない」ように見えるのです。
さらに追い打ちをかけるように、DESI(デジ)という巨大な観測プロジェクトの最新結果が追加されました。
DESIは、宇宙にある多数の銀河や銀河団から届く光の波長を測り、その距離や動きを統計的に調べることで、宇宙がこれまでどのような速度で膨張してきたのかを再現しようとする計画です。
その解析から、「ダークエネルギーの強さが、時間とともに少しずつ弱くなってきているように見える」という傾向が報告されました。
本来、ダークエネルギーの正体が「真空のエネルギー」であるなら、その密度は時間がたっても変わらないはずです。
もしこれが本当なら、「一定の宇宙定数」というΛCDMの前提が揺らぐことになります。
こうした観測上の“モヤモヤ”に加えて、もっと根本的な理論上の悩みもあります。
量子論に基づいて計算すると、「真空のエネルギー」は、観測されるダークエネルギーよりも10¹²²倍も大きくなってしまうという、途方もないギャップ問題も古くから知られています。
宇宙がどんどん膨張して空間の体積が増えていくと、そこに満ちているダークエネルギーの総量も増え続けることになり、「エネルギー保存の考え方とどう折り合いをつけるのか?」という疑問も生まれます。
このように、膨張する宇宙の標準モデルは、多くの部分では非常によく働いているものの、細部をのぞき込むと、あちこちに小さな不一致が見つかり始めています。
ハッブル定数、S₈、ダークエネルギーの時間変化、真空エネルギー問題――これらは別々の“トラブル”のように見えますが、もしかすると同じ根っこから生えているのかもしれません。
そこで研究者たちは発想の転換を行い「宇宙が膨張しているのではなく、私たちの物質世界が縮んでいる」と解釈することで、これら問題が解決できるかを調べることにしました。
宇宙誕生から物質世界が3~4割縮んでいる

ここで大事になってくるのが、「私たちは何を基準に宇宙を測っているのか」という視点です。
距離を測るとき、私たちはメートルという単位を使いますが、その裏には「原子の振動」や「光の速さ」といった、もっと根っこの物理量があります。
時間を測るときの秒も、ある原子が一定回数振動する時間を基準に定義されています。
言いかえれば、私たちが宇宙を観測するときには、いつも「物質世界で決めたものさし」と「物質世界の時計」を通して宇宙を眺めていることになります。
もしこの「ものさし」や「時計」そのものが、宇宙の歴史の中でほんのわずかずつ変化していたとしたらどうなるでしょうか。
例えば、自分が持っている定規の方が年々少しずつ縮んでいたら、同じ壁の長さを測っても「昔は10センチだったのに、今測ると15センチになっている」と感じてしまうかもしれません。
本当は壁の長さは変わっていないのに、「世界の方が伸びた」と勘違いしてしまうわけです。
時間の刻み方が変わる場合も同様で、昔の1秒が今より長かったり短かったりすれば、「変化の速さ」についての見え方は大きく変わります。
今回の論文は、まさにこの「ものさしの側が変化しているかもしれない」という発想を、宇宙論のレベルにまで引き上げたものです。
研究者は、宇宙全体の背景としての時空と、物質世界の時空をきちんと区別してモデル化し、「背景の時空はほとんど変わらないが、物質世界の長さや時間のスケールがとてもゆっくりと縮んでいる」と仮定しました。
そのうえで、「そんな宇宙に住んでいる私たちが、今のようなやり方で宇宙を観測したら、どんなふうに見えるだろうか」を丁寧に計算し、冒頭で紹介したハッブル定数やS8、ダークエネルギーの謎にどこまで迫れるかを調べたのです。
その結果、ビッグバンから現在までの間に、物質世界のスケールが少なくとも一割以上、解析によっては三〜四割程度まで小さくなっているとみなすことで、遠方銀河の赤方偏移や超新星の明るさの変化をかなりうまく説明できることが提案されています。
まず、ハッブル定数の食い違いです。
初期宇宙のデータから求めた値が、現在の宇宙から直接測った値より一割ほど小さい、という問題でした。
もし「昔の一秒」が今より長かったなら、同じ出来事を測っても「一秒あたりの膨張の速さ」は小さく見えます。
つまり、時間の単位がゆっくり縮んでいると考えれば、ハッブル定数のズレは自然な結果として現れます。
コラム:世界が縮小したら原子は潰れないのか?
今回の「物質世界がじわじわ縮んでいるかもしれない」という仮説を聞くと、多くの人が最初に不安になるポイントがあります。「え、それって原子の大きさも小さくなるってこと? 電子が原子核に落ち込んで、世界が全部つぶれたりしないの?」という心配です。直感的には、「空間だけがギュッと縮んだら、+の電荷をもつ原子核と、-の電子の距離が近づいて、引き合う力が強くなりそう」と思えますよね。
ところが、量子力学と電磁気学の視点から見ると、原子が安定して存在できるかどうかは、「距離そのもの」よりも、もっと別の“比”によって決まっています。特に重要なのが「微細構造定数」と呼ばれる電子と光と電気の強さのバランスを表す比率や「電子と陽子の質量」の比率です。これらはメートルや秒やキログラムといった単位ではなく純粋な「比率(無次元の比)」です。この比率が崩れない限り、原子が潰れてしまうことはありません。そして「物質世界の縮小」では原子の直径は小さくなるものの原子を保つための比率は変化しません。そのため物質世界が“外側から”見て小さくなっていたとしても、内側に住んでいる私たちと原子から見ると、状況はずっと変わっていません。電子は、昔も今も「ほどよい距離」を保って原子核の周りを運動し続けます。
同様に物質世界の縮みがブラックホール化を起こす心配もありません。ブラックホールになる条件も、実は「密度の絶対値」ではなく、「重さと大きさの比」で決まっています。もし物質世界の縮小が、「重さ M と大きさ R が同じ割合で縮む」という全般的な縮小ならば物体もブラックホール化することもないのです。
原子やブラックホールの維持において絶対的な距離や密度ではなく、単位の無い無次元の比率に依存しているというのは非常に興味深い事実です。
宇宙のデコボコ具合を表すエスエイトのズレも同じです。
本来なら、重力で物質が集まるので、宇宙は時間がたつほど「ダマだらけ」になっていくはずです。
しかし観測では、初期宇宙からの予想より、今の宇宙のエスエイトが少し小さいように見えます。
ここでも、「昔の一秒が長い」「昔の一メートルが大きい」とすると、成長のしかたを換算し直さなければならず、その補正を入れると、エスエイトのズレは「物質世界のスケールが少なくとも一割以上縮んだ」サインと解釈できる、と著者は述べています。
次に、宇宙の加速膨張を示す決定的証拠とされたIa型超新星の暗さです。
遠方の超新星は、予想より二割ほど暗く見えることから、「宇宙の膨張が加速している」と考えられてきました。
ところが“縮む宇宙”の立場では、超新星が光を出した当時は、今よりも時間の単位が長かったとみなします。
出された光の総量は同じでも、「一秒あたりに届く光の数」は、今の短くなった一秒で数え直すと少なくなり、超新星が暗く見えるのです。
この効果を時間の流れ全体にわたって計算すると、宇宙誕生から現在までに、物質世界のスケールはおよそ三〜四割ほど小さくなっている、という数字が得られます。
DESI の観測が示した「ダークエネルギーの密度が時間とともに減っているように見える」という結果も、このモデルでは自然に出てきます。
著者は、いくつかの「縮み方」のパターンを数式で表し、現在の宇宙ではダークエネルギーによる見かけの押し広げる力が、昔より弱くなっているように見えることを示しました。
特に、物質世界のスケールが指数的に小さくなるモデルや、真空のエネルギーがだんだん効きやすくなるモデルを使うと、DESI のグラフにかなりよく重なるカーブが出てくると報告しています。
さらにおもしろいのは、最近見つかった「超新星の年齢バイアス」と呼ばれる現象とのつながりです。
これは、どんな年齢の銀河に属しているかによって、超新星の平均的な明るさに少し差がある、というものです。
観測では、その差は「十億年(およそ10億年)あたり約0.03等級暗くなる」というきれいな傾きで表されます。
またモデルから計算した「スケールの影響による暗くなり方」は、この傾きとほぼ同じ値になり、超新星データにその補正を入れると、DESI が行ったさまざまな解析結果が互いによくそろうようになると示されています。
ダークエネルギーについても興味深い解釈が現れます。
背景の真空にある「押し広げる力」は一定だとしても、押される側の物質の世界が縮んでいけば、その力が届く「面積」は時間とともに小さくなります。
その結果、物質側の住人から見ると、「ダークエネルギーの効き目がだんだん弱くなっている」ように観測されるのです。
著者はこれらの結果を踏まえて、「物質世界が約三〜四割縮んでいる」と仮定すると、ハッブル定数のズレ、エスエイトのズレ、超新星の暗さと年齢バイアス、DESI が見たダークエネルギー密度の減少など、いくつもの現象が同じ方向で理解しやすくなる、と主張しています。
既存の観測と理論の間に存在するいくつもの不一致を、気持ちいいくらいに一本の解釈である程度説明できそうだという結果は、まだ仮説段階ではありますが、とても刺激的だと言えるでしょう。
かつてアインシュタインは光の速度こそが不変であり、時空のほうが歪むという既存の価値観がひっくり返るような理論を打ち立て、現在の物理学はそのひっくり返った常識の上に打ち立てられています。
もしかしたら今後の研究により、宇宙が膨張していたという前提がひっくり返り、実は私たち物質側が縮小していたという前提で物理学が進展していくかもしれません。
「縮む物質」が宇宙論に投げかける問い
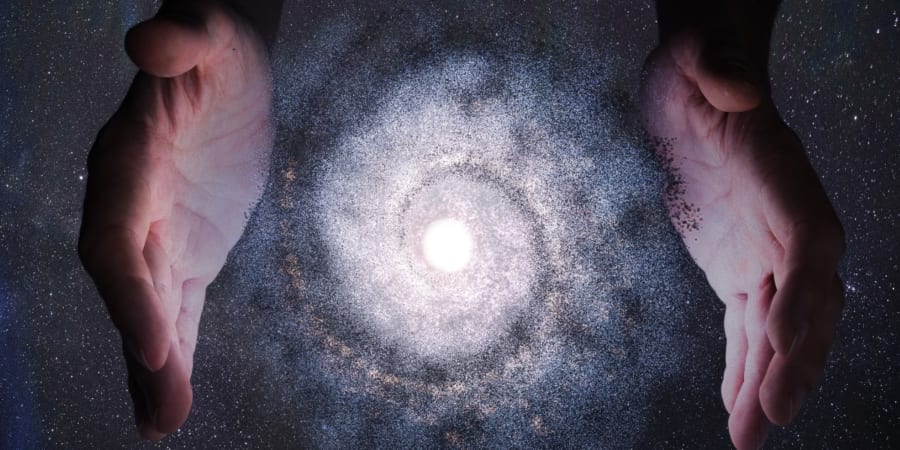
この“縮む宇宙”仮説のいちばんの意義は、「宇宙が膨張している」という、ごく当たり前に見える前提に挑戦し、予想以上の善戦をみせた点にあるでしょう。
観測そのものは何も変えていないのに、「何が動いているのか」「どちらを基準にものさしを当てるのか」という視点を入れ替えるだけで、ハッブル定数のズレやエスエイトのズレ、ダークエネルギーの減少傾向などを一つのストーリーで説明しなおせるかもしれない可能性が示されたのです。
また理論的な観点から見るても、この仮説にはいくつか魅力的なポイントがあります。
ひとつは、ダークエネルギーの「エネルギーはどこから来るのか」という疑問をやわらげる可能性があることです。
宇宙空間そのものがどんどん増えていくと、空間にふくまれるエネルギーも増え続け、エネルギー保存の感覚からすると落ち着きません。
しかし「本当は物質世界のほうが圧縮されていて、宇宙の土台はほぼ一定」とみなせば、むしろ全体としてエネルギーが少しずつ元のゼロの状態へ戻っていく、というイメージに変わります。
また、遠い銀河が光速より速く遠ざかっているように見える「超光速問題」や、宇宙がなぜこんなに平らなのかという問題、真空エネルギーが計算上は観測値のとてつもない倍率になってしまう問題なども、スケール収縮の枠組みではより素直に解釈できるようになります。
今後の大きな課題は、「本当にテストできるかどうか」です。
縮み続ける定規しか持てない私たちに、「今ここ」で起きている物質世界の縮小を検知することは困難です。
ただ宇宙規模ではそれが可能かもしれません。
宇宙では遠方を見ると言うことは、過去を見ることです。
たとえば10億光年離れた場所を観測することで、10億年前の宇宙の状態を知ることが可能です。
今後の観測でさらに遠い超新星や銀河、重力波などのデータがたまれば、「縮む宇宙」が本当かどうかがわかるでしょう。
著者自身も、現状の宇宙論にスケール収縮のパラメータを組み込み、宇宙の誕生から現在までのすべての時代を通して、観測データと突き合わせ直す必要があると書いています。
もしかしたら未来の科学雑誌には「天動説」や「地球平面説」と同じ項目に「宇宙膨張説」があり「昔の人は宇宙が膨張していると考えていた」と解説されているかもしれません。
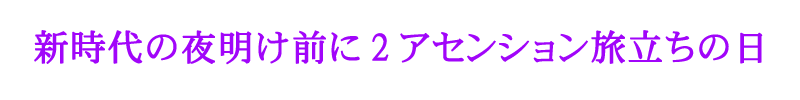


コメント