専門用語の出現頻度を指標としたところ、特許の創造性が低下していることが明らかになった。ヒトがAIに依存し思考を放棄した結果。
2026年、科学の世界でパラダイムシフトを巻き起こすような画期的な発見は生まれないだろう──。一見すると、これはさほど突飛な予測ではないかもしれない。そもそも時代を反映した考えや規範を意味する「パラダイム」というものは、そう簡単には変わるものではないからだ。だが、26年にわたしたちが目の当たりにするであろう科学の進歩の停滞は、より根深く、大いに憂慮すべき問題の兆候と言えるだろう。というのも人類は、その創造性を失いつつあるからだ。
とはいえ、知的能力が減少しているわけではない。実際、IQスコアは過去100年にわたる大半の期間で着実に上昇を続けており、この現象は「フリン効果」として知られている。平均スコアを100に維持するため、IQテストの実施機関はテストのRawデータを繰り返し再調整する必要に迫られてきたほどだ。
これと同様の変化は、創造性を測る最も一般的な標準テストである「トーランス創造的思考テスト」でも見られる。ただし、結果が示すベクトルの向きは正反対だ。
ウィリアム・アンド・メアリー大学のキム・ギョンヒの分析によれば、トーランステストのスコアは1960年代から90年代まで安定していたものの、その後、低下のトレンドをたどっている。さらに2008年までには、テスト項目の一部でスコアが劇的に低下し、10年代に入るとそのペースはさらに加速しているというのだ。
この傾向がすでに現実世界に影響を及ぼし始めていることを示唆する兆候もある。セントルイス連邦準備銀行のエコノミスト、アーカシュ・カリヤニが24年に発表した分析で、新たな専門用語の出現頻度を指標としたところ、特許の創造性が低下していることが明らかになった。これは、ミネソタ大学が以前に行なった4,500万件の科学論文と390万件の特許を対象とした研究結果とも呼応している。
この研究では、論文が過去の知見を単に融合するだけではなく、対象とする分野全体の研究の方向性に与えたインパクトについて指標を用いて分析することで、研究者・発明家たちの「ディスラプティブ」な影響力がここ数十年で着実に低下していることが示された。
これは、特定の分野で手の届きやすい果実(より確実な結果の得られる研究)がすべて摘み取られてしまったという単純な話ではない。物理科学、社会科学、生命科学といった分野でも、ディスラプティブな影響の度合いは、同程度の期間内に同様の低下傾向を示しているのだ。
その結果、新しい論文や特許は──複雑系理論の研究者であるスチュアート・カウフマンが「隣接可能領域」として指摘したように──過去の発見を土台に少しずつ積み重ねられていく傾向をますます強くしている。これは、わたしたちがWikipediaに新たな情報を追加したり、Spotifyでそれまで聴いたことのない音楽に遭遇したりするプロセスと似ている。ある曲を気に入れば、同じアーティストの別の曲や同じジャンルの曲を探し、それがまた隣接する新たな可能性の扉を開くのだ。
しかし、真に斬新な発見は、より大胆な想像力の飛躍や、予期せぬつながりから生まれるものだ。実際、ベルギーと米国の科学者によると、これまで同時に引用されたことのないふたつの学術誌の先行研究を引用している論文のほうが、突出して破壊的な影響力をもつ傾向があるという。
映画や音楽の分野でも
映画の世界でもまた、創造性の低下を示す兆候が見られる。1981年、ハリウッド映画の興行収入トップ10のうち、続編だったのは『スーパーマンII』と『007/ユア・アイズ・オンリー』のわずか2作品だった。この数字は91年には3作品、2001年には5作品、そして11年には8作品へと増加する。そして22年になると、トップ10のすべてが続編かリブート作品で占められるまでになったのだ。
音楽の世界に目を向けると、オーストリアの研究者グループが50年間にリリースされた12,000曲のポップソングを分析した結果、歌詞がより単純で反復する傾向になっていることを発見した。また、ビルボードの「Hot 100」チャートにランクインする新人アーティストは減り、現在ではかつてよりもチャートが既存のヒットメーカーに独占される傾向が強まっている。
これら多様なかたちで表れる創造性の低下を、たったひとつの決定的な要因で説明することはできない。キムは、トーランステストのスコア急落の原因を、学校における標準テストの増加と、体系化されていない「自由な遊び」の減少にあるとしている。ある試算によれば、子どもたちが自由に遊ぶ時間は1980〜90年代にかけて25%減少し、過去10年間のスクリーンタイムの増加がこの問題を劇的に悪化させている。
ミネソタ大学の研究チームは、科学における破壊性の低下の一因を、「論文を発表できなければ終わり」という科学界の文化にあると指摘する。これは、研究資金を得るために短期的な成果を優先させ、画期的な発見をもたらす可能性のある、探究的な基礎研究に割く時間的余地はほとんど存在しないという弊害をもたらす。
しかし、26年を転換点たらしめるのは、人工知能(AI)の絶え間ない進化だ。25年初め、トロント大学のコンピューター科学者たちは、大規模言語モデル(LLM)が創造性に与える影響について実施した研究結果の(査読前の)学術論文を公開した。1,000人以上がこの研究に参加し、例えばタイヤや瓶といった日常的なモノの新しい使い道を考えるといった、一連の標準的な創造性タスクを、ChatGPTの助けを借りる場合と借りない場合の双方で行なったのだ。
いくつかの事例では、AIが被験者の短期的なパフォーマンス向上に貢献したことが判明したものの、その後、AIの助けなしで同じタスクを繰り返したところ、以前にChatGPTを利用した被験者たちの創造性は低下傾向を示した。つまり被験者たちが生み出すアイデアは多様性を欠き、より画一的なものになっていったのだ。
言い換えれば、この「創造性の危機」は2026年にさらなる悪化の一途をたどるということだ。この流れをどう食い止め、反転させるか。それを解き明かすためには──残念ながら──創造性そのものが求められている。
アレックス・ハッチンソン|ALEX HUTCHINSON
サイエンスジャーナリスト。持久力や探求心の科学をテーマに、人間の身体的・精神的な限界を研究し、その科学的知見に基づく鋭い分析で知られる。著書に『限界は何が決めるのか?』『The Explorer ’s Gene』がある。
(Originally published in the January/February 2026 issue of WIRED UK magazine, translated by Oval Inc., edited by Michiaki Matsushima)
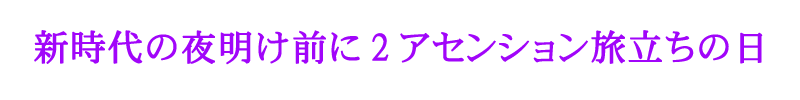
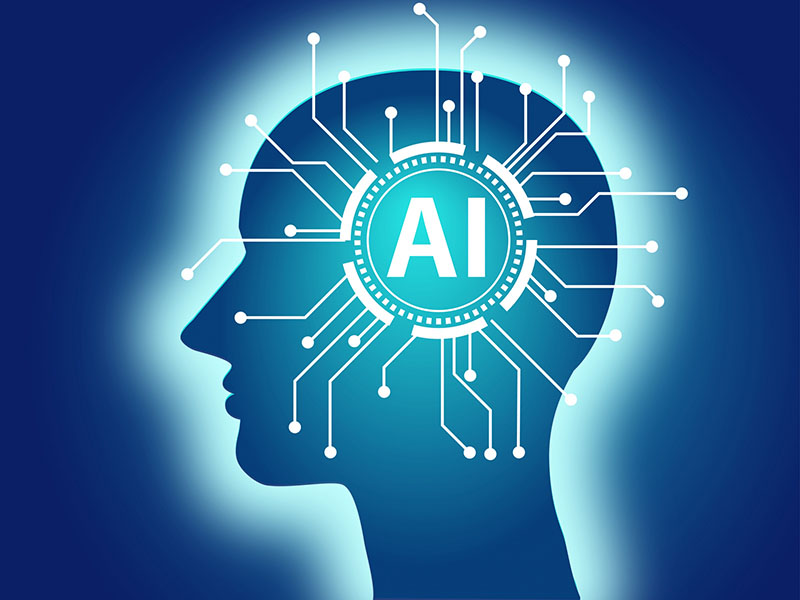


コメント