WHOメルトダウン!厚労省のいう「科学的根拠や信頼できる情報源」とはなんですか?
WHOメルトダウン! – トランプ大統領がWHOから資金を引き揚げたことで、テドロス事務局長は完全にメルトダウン状態だ!
「我々はロックダウンもマスクもワクチン接種義務も課していない…そんな権限はない!」 – テドロス事務局長はダメージコントロールに奔走している。
トランプ大統領がWHO離脱を主導し、各国が追随する中、テドロス事務局長はビル・ゲイツの代弁者であり、長年にわたる世界的な影響力拡大と製薬大手による金儲けの末に中国の傀儡だったことが暴露された。そして今、彼は罠が解ける中、皆をガスライティングしている。主権が勝利し、グローバリストエリートは大敗!
🚨複数の立法者、国際機関、そして査読済みの科学論文が、mRNA注射が生物兵器または技術的大量破壊兵器に該当すると宣言しています。
✅ アリゾナ州法案 HB 2974
✅ ミネソタ州法案 HF 3219
✅ 先住民族連合
✅ American Journal of Physicians and Surgeons に掲載された査読済み研究
✅ 1989年米国生物兵器・テロ対策法の起草者、フランシス・ボイル博士(宣誓供述書)
✅ 世界保健評議会
↓
注射剤が、広島の核攻撃100回分以上の死傷者をもたらすような場合、それは規制論争の問題ではなくなります。それは刑事責任、立法介入、そして歴史的説明責任の問題となります。
信じられない!RFKジュニアが衝撃的な爆弾発言:過去36年間のワクチン被害報告において、COVID-19ワクチンは他のすべてのワクチンを合わせたよりも多くの報告された被害と死亡が関連付けられている。
それなのに、まだ投与されているのか?


COVIDワクチンの最も不可解な部分は、接種を受けていない人々にも「拡散」して害を及ぼすその能力です。私がここで評価してきた数千件の拡散報告を、査読済みの研究がまさに検証しました。
この謎を解き明かすために、あなたの体験談をぜひ共有してください。
学会員の近所のおばちゃん、『コロナワクチンこんなに早く打てるようになったのは公明党のおかげ』と自慢してた。私は当時、先行接種した海外で酷い副作用報告があるから打つなといったのに、打った。旦那さんは4回目接種時に腕に強い電流を流したかのような衝撃が走り、その後に寛解してた癌再発と全身転移、持病の坐骨神経痛悪化で歩行困難になり死亡。ワクチンについてド素人の情弱なのに推しまくった公明党も創価学会員も、あまりに無責任です





厚労省のいう「科学的根拠や信頼できる情報源」とはなんですか?

医学には「害を成すな」という原則が存在すると一般に言われている。しかし、害を前提として構築せざるを得ない医学実践において、この原則は如何なる意味を持ち得るのか。
治療は本質的に侵襲的であり、常に未知のリスクを伴う。さらに、無治療という不作為それ自体も害を生む可能性を孕む。不確実性が不可避である限り、絶対的な意味での「害を成すな」は原理的に作動し得ない。
それでもなおこの原則が掲げられるならば、それは「害を生じさせるな」という命令ではなく、「害を制度的に処理可能な形で生じさせよ」という功利的定式へと翻訳せざるを得ない。
この意味において、医学は害の可能性を排除する体系ではなく、害の可能性を確率統計的に管理し、配分する体系として成立する。
したがって、医薬品の副作用、手術の合併症、治験での有害事象はいずれも「想定外の事故」ではなく、制度設計の段階から予め織り込まれた「想定内のコスト」として処理される。
この文脈に従えば、インフォームド・コンセントやリスク・ベネフィット評価は、「害が生じ得ること」を患者や被験者へと転嫁させる免責装置として機能する。
これらの装置を介して害の可能性が説明され、同意が得られたとき、「害」は「制度的に了承された害」へと変換される。つまり、「害」は、「禁止されるべきもの」から「了承されるべきもの」として再定義される。
より残酷に言えば、「害」は医学が患者に対して行う加害ではなく、患者が自ら生じさせたものとして引き受けさせられる自己帰責へと変わる。ここでは害の事実は何一つ変わらないが、それを問う言語が存在しなくなる点が変わる。
最終的な正当性を担保する基準は、「害が生じたか否か」ではなく、「ガイドラインに準拠していたか否か」である。この時点で「害を成すな」という原則は、行為を禁じる倫理的命令ではなく、行為を許可する手続き的要件へとすり替わる。
そもそも「害を成さない」という態度は、人間として生きる以上、最低限の道徳である。それを明示的に唱えるのは、子どもを躾ける時か犯罪者に道徳を説く時である。愛する人を抱きしめる時にリスクを計算し、「非害の成立」を確認する者はいない。
それが余りに自明で純粋であるが故に、医学がそれを敢えて原則として掲げざるを得ないのは、医学内部の道徳が初めから欠落しているからである。
逆説的であるのは、医学がその原則を敢えて掲げることで「害を成すこと」が却って許容される空間が広がる点である。まるで「害を成すな」と宣言しさえすれば、それ以外の場所では害を成してもよいかのように。
この地平において「害を成すな」という医学原則は既に死んでいる。それは、制度的必然性によって殺され、保存され、展示されているのである。
死んだ倫理は静かに佇むが、反論することも告発することも責任を問うこともない。医学の内部空間を漂っているのは、その原則が今なお生きている幻想と、そこから立ち上る死臭である。
手続き的、形式的な条件が揃った瞬間、たとえ人が死のうが後遺症を負おうが、その出来事が本来突きつけるはずの道義的・人間的な問いは語ることすら許されなくなる。
代わりに「不幸な事故」、「多くの命が救われた」、「より安全な製品開発に努める」といった定型句が事後的に添えられ、倫理的責務が果たされたかのような物語が演出される。
「害」という事実が「技術的な課題」や「手続き上の問題」へと翻訳されると、人は「死んだ人」ではなく「アウトカム」になり、実際に生じた被害の具体性は剥奪される。
インフォームド・コンセントの基礎となったニュルンベルク綱領の第一原則は、同意の成立条件として以下を要求していた。
(1) 法的能力
(2) 自由な選択権
(3) 強制、詐欺、欺瞞、強迫、強要の不在
(4) 十分な知識と理解力
(5) 理解と啓蒙された判断
(6) 受諾前の完全な開示
これはナチスの医療犯罪に対する深い反省の文脈の中で生まれ、「同意」は「結果」ではなく「被験者の能力と状態」として定義された。
しかし、現代の医学は「同意」という形式のみを温存し、それ以外の条件を形骸化させている。
そして、医学はパンデミックにおいて「希望書」という新たな概念装置を導入した。医学は、もはや「同意」というフィクションを経由せずに害を処理する技法を発明したのである。
パンデミックは医学にとって「例外状態」ではなく「本音が吐露した瞬間」である。医学は自分が何をしているかを隠す必要すらなくなった。
医学に触れた倫理は、たとえ崇高な理念を掲げていようが出来事に内在する問いとしての力を必然的に失い、制度を防衛する言語装飾へと転落する。この転落は高度に制度化された専門知の宿命である。
それは決して未来を拘束する規範ではなく、過去の加害性を正当化し、未来の加害性へと接続する回顧的付加物として機能する。
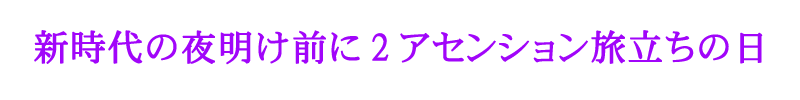



コメント