どのような知見があろうとも3I/ATLASは彗星であるという主張に変わりはない
「宇宙人の乗り物」が太陽系内に…? Xデーは10月29日、ハーバード大教授「休暇はXデーの前に」
https://news.yahoo.co.jp/articles/d23384df725d4c16a3f9b733cf05d3556f2d56f4
●●●●以下転記はじめ●●●●
7月に観測された恒星間天体「3I/ATLAS」は、ただの彗星というには異常な点が多いハッブル望遠鏡が捉えた「3I/ATLAS」。
果たしてその正体とは ZUMA Press Wire via Reuters Connect-REUTERSまもなく太陽への最接近を迎える恒星間天体「3I/ATLAS」。
これまでに発見された中で3番目の太陽系外からやってきたこの天体は、科学者たちを大きく興奮させている。
【動画】
「3I/ATLAS」は宇宙人の乗り物なのか?
ミシガン州立大学のダリル・セリグマン物理・天文学部教授は本誌に「これは非常にエキサイティングな発見だ」と興奮気味に語った。 本誌はNASAにもコメントを求めたが、返ってきたのは自動返信メールだった。「NASAは現在、政府の資金停止により閉鎖中です。
このメールボックスは監視されていません」 恒星間彗星は極めて稀であり、3I/ATLASの発見は惑星科学者の興味を大いにそそった。
ペンシルベニア州立大学の天文学・天体物理学教授であり、同大学の地球外知性研究センター所長でもあるジェイソン・ライトは「観測できた恒星間彗星は、3I/ATLASを含めても3例しかない。
そのため、惑星科学者たちは恒星間彗星を観測できる機会が巡ってきたことに、大いに興奮している」と本誌に語った。
「彗星は、惑星と共に恒星が誕生する初期段階で形成される……
大半は恒星の周囲にとどまっており、時折恒星に近づいて尾を形成する。しかし、一部の彗星は、惑星の重力によって恒星系からはじき飛ばされ、恒星間を漂うことになる」3I/ATLASとは?
3I/ATLASは7月1日に、NASAが資金提供しているチリのコキンボ州リオ・ウダルトにあるATLAS(地球衝突小惑星最終警報システム)望遠鏡によって初めて発見された。
「3I/ATLAS」という名称もこの時に与えられた。
発見当時、3I/ATLASと地球からの距離は約6億7000万キロメートルだった。
NASAは地球への最接近時でも2億4000万キロメートル以上の距離を保つことなどを踏まえ、この天体が「地球に脅威を与えることはない」と発表している。
3I/ATLASの前に発見された恒星間天体は、2017年に発見された「1I/オウムアムア」と、2019年に発見された「2I/ボリソフ」の2つだけだ。
セリグマンは「これらの天体が銀河の他の場所から来たものであることは、軌道が双曲線であることから明らかだ。太陽系に縛られることなく、飛び去っていくだろう。(太陽系に)再び戻ってくることはない」と述べている。
3I/ATLASは「宇宙人の技術」?科学界では、3I/ATLASは彗星だという見解が広く受け入れられている。
セリグマンは、「彗星活動の明確な証拠がある。発見当初から現在に至るまで、その振る舞いは太陽系内の彗星と完全に一致しているのだ」と述べた。 一方、ハーバード大学の教授であり、理論計算研究所の所長でもあるアブラハム・アビー・ローブは、3I/ATLASが「宇宙人の技術」である可能性がわずかに存在すると主張している。
その根拠として、ローブは、3I/ATLASがこれまで発見された2つの恒星間彗星よりも明らかに大きく、より高速で移動していること、太陽に最も近づく時点で「地球からは観測できなくなる」こと、「周囲のガスの中に含まれるニッケルの量が鉄よりも多い」ことなど、複数の「異常」を挙げた。
3I/ATLASのおかしな点は、2019年の恒星間天体でも宇宙人の可能性が囁かれている中でも、科学者たちは3I/ATLASは彗星とのスタンスを崩さない。ライトは3I/ATLASの「異常」について、「多少の奇妙さはある」としつつも、「大して驚くようなことではない」と述べている。
その理由として、太陽系内の彗星も「非常に多様である」こと、そして、3I/ATLASが「別の恒星系から来たものなのだから、ある程度違っていて当然」であることを挙げている。
「こうした違いは、他の恒星系がどのようにして惑星を形成するのかを知る手がかりになる」 また、ニッケル量についても、ニッケルを含む彗星も少なくないため、特別奇妙なことではないという。
セリグマンによると、太陽に近づいた一部の彗星では、「塵の中に含まれるニッケルが蒸発し、蒸気として観測される」ことがある。
この現象は「通常、3I/ATLASが現在存在している環境よりずっと高温の環境で起こる」が、「太陽系内の彗星や、2019年に飛来した恒星間彗星2I/ボリソフでも観測された」と指摘した。
「ニッケルが昇華するには温度が低くなりすぎるような構成から遠く離れた場所でニッケルが観測されるというこの現象は、太陽系を周回する彗星でも確認されている。
おそらくこれは、3I/ATLASの氷の構造が複雑なためであり、他の物質とともにニッケルが氷の中に取り込まれていることを意味している」10月29日がXデーになるかも?天体が太陽に最も接近した時の到達点を「近日点」という。3I/ATLASは10月29日に近日点に到達すると予測されている。
そして、近日点に到達する時こそが、彗星の構成物質を観測する上で、理想的な条件が整う時期とされる。 「すべての彗星は、太陽に接近する軌道を持っている」とセリグマンは述べた。
そしてその時に、「彗星は最も直接的に太陽光を浴び、最も熱を持つ」と付け加えた。
この温度上昇により、さまざまな種類の氷が「それぞれの温度で活動を開始」し、「可能な限り多くの氷が活性化する」ことになるという。
「彗星の近日点近くでの観測は、いわば最も効率のよい観測機会だ。
彗星の構成を最も包括的に捉えるチャンスとなるからだ」 一方、ローブは3I/ATLASの軌道に疑問を呈している。
3I/ATLASを観測する最も適した時期は「ちょうどそれが地球から観測不能になる時期と重なる」という。
「これは単なる偶然なのか、それとも軌道設計と宇宙航法の原則に基づいたものなのか」 またローブは、女優で神経科学博士のマイム・ビアリクがホストを務めるポッドキャスト「ビアリク・ブレイクダウン」で、次のように述べた。
「休暇を取るなら(3I/ATLASが近日点に到達する)10月29日より前に取るべきだ。その日何が起こるかは誰にも分からないのだから」
しかし、ライトは3I/ATLASの軌道について「特別な意味はない」としており、「彗星が太陽の反対側に抜けた後、再び観測できるようになる」と述べている。 NASAによれば、3I/ATLASは12月初めには太陽の向こう側から再び姿を現す見込みである。
インターネットでは3I/ATLASが宇宙人の乗り物であるという都市伝説がまことしやかにささやかれている。
果たして、人類は無事に10月29日を乗り越えることが出来るのだろうか。
●●●●以上転記おわり●●●●
地球最接近が目前のアトラス彗星は葉巻形UFOだった! 火星探査機が捉えた巨大母艦に天文学者も警告
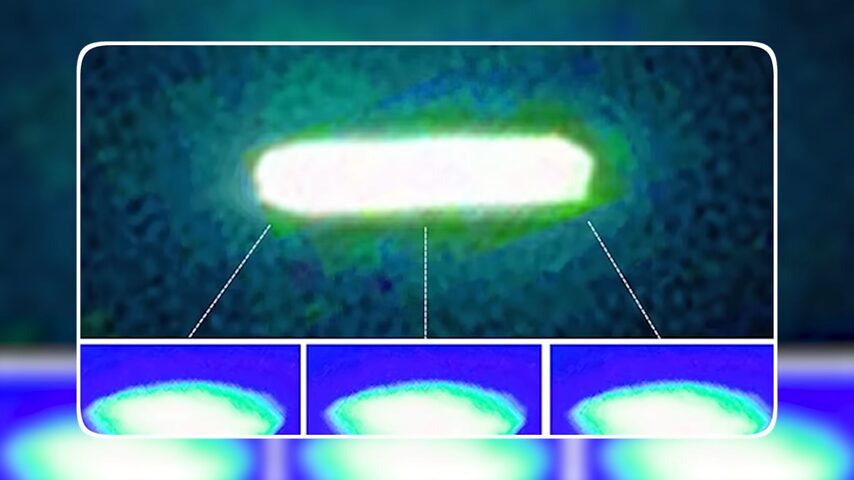
マイコメント
果たしてどうなるのだろうか?
私の考えとしてはそれほど騒ぐこともないと思われるのだが・・・。
もし、宇宙的脅威だとしたら、異星人のテクノロジーを考えればとっくのうちに
地球が侵略されていても良さそうなものです。
それが起きてないという事はそう大きな問題でもないという事です。

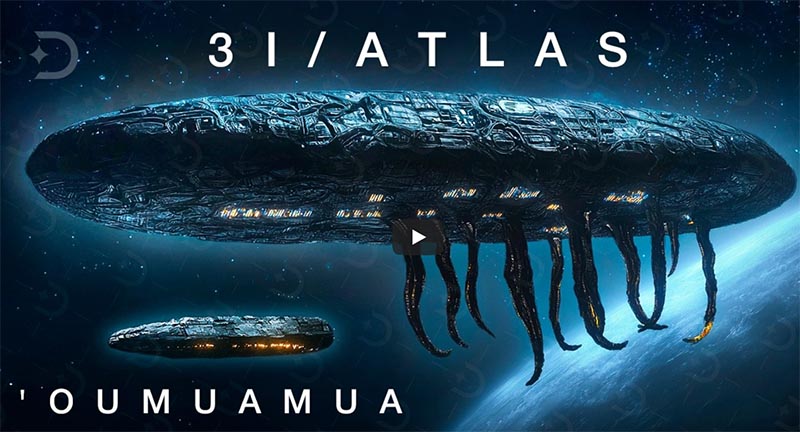



コメント