安倍首相の側近”だった高市内閣のキーパーソンの名前
※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中」の一部を再編集したものです。
財務省との対決姿勢が鮮明
10月21日、高市早苗氏が自民党総裁として、内閣総理大臣に就任した。所管指名選挙を経て、正式に総理大臣の職に就いた。
直ちに組閣本部が設置され、閣僚名簿が発表された。この閣僚名簿を見る限り、非常に重大な事態が始まったという印象を受けた。
いくつかポイントがあるが、最初に注目すべき点は、高市新総理が財務省に対して挑戦状を叩きつけたということである。
私が最も注目していたのは、財務大臣のポストと経済財政担当大臣の人事であった。果たして、誰がその重要ポストに就任するのかという点に関心を寄せていた。
結果として、財務大臣には片山さつき氏が、経済財政担当大臣には城内実氏がそれぞれ就任した。城内氏は、前・石場政権下において経済安全保障担当大臣を務めていた人物であり、今回は経済財政担当大臣へと横滑りする形となった。
なぜこの人事に注目していたのか。それは、高市総理が本当に積極財政の方向へと舵を切るのか、それとも政権をスムーズに離陸させるために財務省との融和路線を取るのか、という点を見極めたかったからである。
今回の人事を見る限り、高市政権は財務省に対して真っ向から勝負を挑んだ構図となっている。
経済財政担当大臣、城内実氏とはどういう人物か
中でも注目したいのは、経済財政担当大臣に就任した城内氏である。
言うまでもなく、城内氏は高市氏の過去3回にわたっての総裁選出馬に際しては一貫して同氏を支持してきた人物である。特に前々回の総裁選では、安倍元首相の意向を汲み、高市陣営の事実上の選挙対策責任者として、城内氏が陣頭指揮を執る形で総裁選を戦った。いずれにしても、城内氏は一貫して高市氏を応援し、支援してきた立場にある。
城内氏のもう一つの顔は、「責任ある積極財政を推進する議員連盟」の顧問であることだ。この議員連盟は、自民党内に設けられたものであり、通称「積極財政議連」と呼ばれ、かつては「安倍別動隊」と目されていた議員グループだ。
この議連の立ち上げにあたっては、安倍晋三元首相の強い意向が働いていた。そのため、安倍元首相はこの議連の会合にもたびたび顔を出していたという経緯がある。
そして、その安倍元首相の側近中の側近とされる城内氏が、顧問としてこの積極財政議連の中心的な役割を担ってきた。なお、共同代表には中村祐之衆院議員、杉本尚衆院議員、若林洋平衆院議員が名前を連ねている。
恒久的な消費税減税を主張
この積極財政議連の過去の動きで最も注目されたのは今年5月8日のことである。
この日、自民党内の積極財政派、特に参議院選挙において「消費税減税」を選挙公約に掲げるべきだと主張する議員グループが動きを見せた。こうした主張を行ういくつかの議員連盟の中核を担っていたのが、前述の積極財政議連である。
このグループは、5月8日に森山裕幹事長に対して5つの提言書を提出した。
この提言書の内容は、「軽減税率8%が適用されている品目について、これを消費税0%へと恒久的に減税すべき」というものであった。期間限定の措置ではなく、恒久的な減税を主張していた点が特徴である。
自民党内に潜む積極財政派の存在
しかしながら、この提言に対しては、森山幹事長および当時党税制調査会長を務めていた宮沢洋一氏によって握り潰される形となった。
だが、この提言書には自民党所属の国会議員96人が賛同し、署名を行っていたという事実は重い。
当時、自民党所属の国会議員数は約300人であった。そのうちの約3分の1にあたる96人が、自らの名前を出して、署名・捺印を行ったという事実自体が極めて注目に値する。
当時の自民党執行部は、いわゆる「バリバリの緊縮財政派」で構成されていたため、このような提言書を提出することは、党執行部から睨まれたり、圧力や嫌がらせを受けるリスクを伴っていた。それにもかかわらず、96人もの議員が実名を出して賛同したという事実は極めて重い意味を持つ。
内心では賛同していながらも、署名したことによる不利益を懸念し、やむなく署名を見送った議員も相当数いたことは間違いない。
そして、そうした議員たちを取りまとめる役割を担っていたのが、他ならぬ城内氏であった。
国の経済運営を担う重要ポスト
そして城内氏が経済財政担当大臣に就任したことは、極めて大きな意味を持つものである。
一般にはあまり知られていないが、このポストは単なる特命大臣ではない。経済財政担当大臣は、内閣の経済そして財政政策の根幹を担う「経済財政諮問会議」の中核的存在である。
経済財政諮問会議の議長は内閣総理大臣が務めるが、この会議を所管するのが経済財政担当大臣である。すなわち、城内氏は総理大臣と並び、国の経済財政運営の方向性に直接関与する立場に就いたことになる。
名ばかりの政治主導だった「骨太の方針」策定
この経済財政担当大臣が担う主な役割の一つが、「骨太の方針」の策定である。
「骨太の方針」とは、正式には「経済財政運営と改革の基本方針」と称され、予算編成作業に着手するのに先立って毎年6月に政府が策定する「次年度予算方針」とでもいうべきものである。つまりこの方針は、翌年度の予算編成に際し、重大な意味を持ってくるものだ。
この方針の重要性が広く認識されるようになったのは、小泉純一郎政権時代のことである。それ以前から存在していたが、特に小泉政権期に注目を集めるようになった。
具体的には、次年度の予算編成作業において、概算要求基準、つまり各省庁が提出する予算要求の上限などを定める際、従来は財務省主導で進められていたプロセスを、政治主導に転換する役割を担ったのが「骨太の方針」である。
この方針を通じて、その年の政権が掲げる予算編成の基本方針、枠組みを明確にし、それを基に概算要求の作業が進められていくという流れが確立された。
なお、この会議の議長は総理大臣であるため、「骨太の方針」はすなわち総理大臣による翌年度予算編成における基本方針を意味する。したがって、この文書の策定は極めて重要であり、その内容は非常に詳細にわたって記述される。
当時、小泉政権下ではこの「骨太の方針」が政治主導で策定されていた。しかしその後、財務省がこの方針策定の主導権を握ることとなる。政治主導から官僚主導へと変質してしまった。
つまり、財務省の影響力が年々強まり、今日においては「骨太の方針」は事実上、財務省が自らの思惑にもとづいて、その中身を決定しているのが実態である。
財務省の牙城に切り込んだ高市総理
これこそが根本的な問題である。
財務省が主導権を握り、さらに総理の意向という名目を得ることによって、緊縮財政が強力に推し進められてきたという経緯がある。
そのような状況下において、積極財政派の城内氏が経済財政担当大臣として乗り込んだことは、従来の流れを大きく転換させる可能性を示している。すなわち、来年度の予算編成が緊縮的なものから積極財政的な方向へとシフトする可能性が、極めて高くなってきたということである。
高市総理大臣は、この状況を十分に意識した上で、自らの腹心とも言える城内氏を経済財政担当大臣に任命した。この人事には高市総理の明確なメッセージが込められていると見ていいだろう。
城内氏の動向に注目したい
現在、財務省はまさに衝撃を受け、緊張感を強めている状況にあると考えられる。いわば、城内ラインと財務省との対立構図が鮮明になり、その戦いの火蓋が切られたのである。
もちろん、来年6月の「骨太の方針」策定までにはまだ時間がある。今後、この攻防がどのような形で展開されていくのか、極めて注目に値する。
高市総理が本当に積極財政を強力に推進していくのか。それとも、財務省が巻き返しを図るのか。現在、これらの動きについて継続的に取材を行っており、引き続き最新の情報をお届けする予定である。
ぜひ、経済財政諮問会議の議論の行方と、そしてその担当大臣である経済財政担当大臣・城内氏の動向に注目していただきたい。
高橋洋一、須田慎一郎『自民党財務省政権 崩壊への最終宣告 「増税脳」の呪縛を解く』(徳間書店)
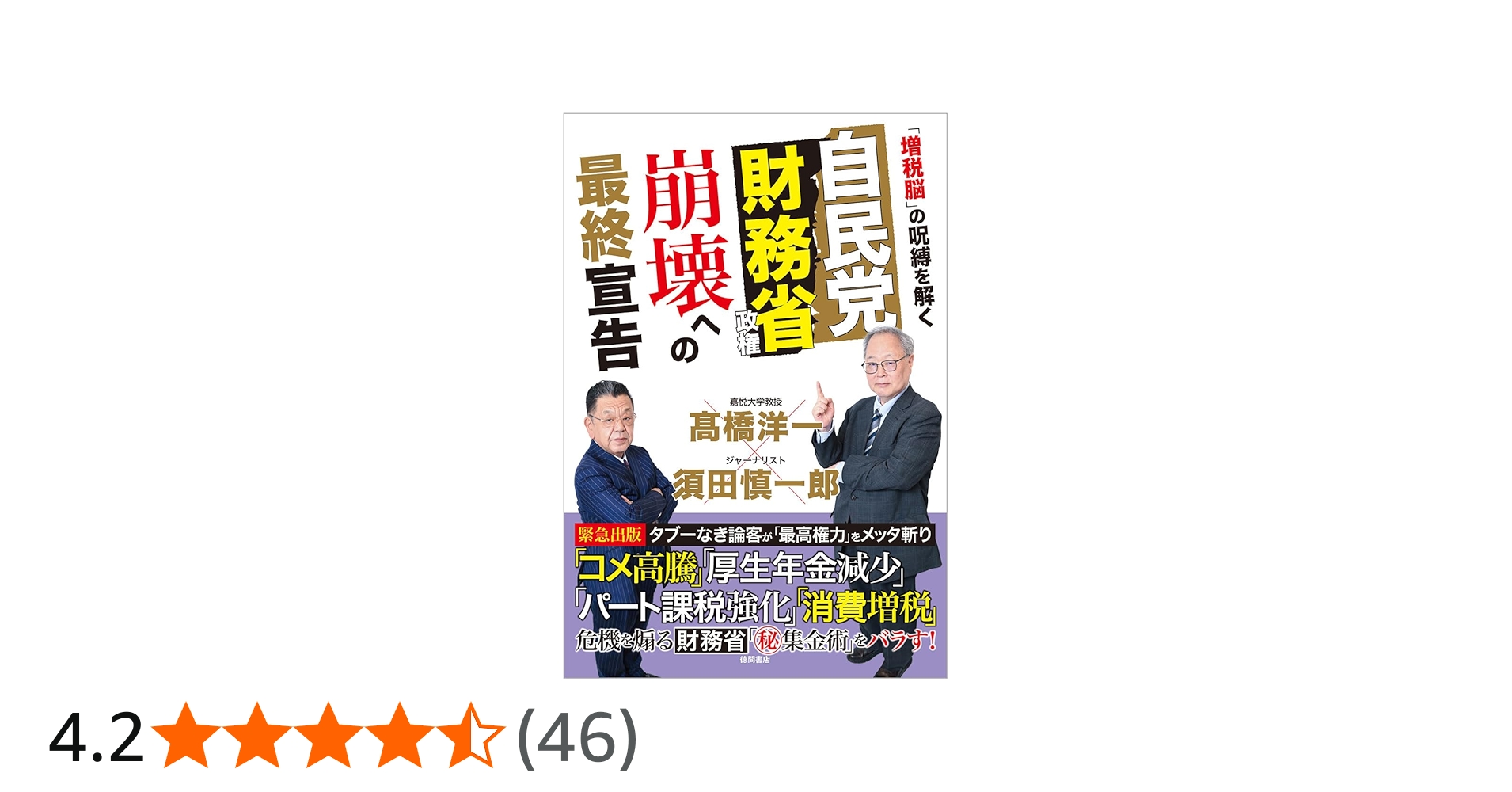
マイコメント
日本経済を30年に渡って沈下させてきた財務省に対して勝負を挑む形となった
高市政権のやり方に対しては応援したい。
今後の政権がどのように財務省に対して対峙していくか注目すべきことであるが
財務省の反発も相当強いだろうと思われます。
気にかかるのは財務省はこれまでも財務省反対派や人物に対して刺客を送りその
人物を失脚させたり亡き者にしてきた前例があることです。
高市政権ではこと財務に関してはそのようなことがないことを祈りたい。






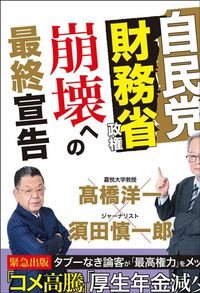


コメント