“カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説
ニンバスの患者で「剃刀の刃を飲んだような」という症状を示した患者は一人もいませんでした。藤田医師
「見事に南から感染の波が……」
新型コロナウイルスの新変異株「ニンバス」。沖縄を皮切りに感染の波は北上中で、着々と迫る“脅威”におびえている人も多いことだろう。気象用語で「嵐雲」を意味するニンバスは、果たしてどれほどの嵐を巻き起こすのか。専門家がその“正体”を解説する。
***
8月15日に厚生労働省が発表したところによると、全国約3000カ所の定点医療機関から4~10日の1週間に報告された新型コロナウイルスの感染者数は、1医療機関あたり6.13人だったという。都道府県別では、宮崎14.71人、鹿児島13.46人、佐賀11.83人と、日本列島の南西方面から感染が広がっていることが分かる。

琉球大学名誉教授の藤田次郎医師が語る。
「沖縄県では5、6月には定点医療機関あたり約20人いたニンバスの患者の数は、8月現在では約半数の10人ほどにまで減ってきています。つまり沖縄におけるニンバスの感染者数は今年5、6月がピークであり、8月現在ではピークアウトしている状況だといえます」
現在、宮崎や鹿児島など九州地方で感染者数が多くなっているのは、
「沖縄から直行便が多く出ていてアクセスの良い地域へと、見事に南から感染の波が広がってきている、ということだと思います。今後感染拡大が予想される東京都をはじめ全国各地の感染状況は、沖縄県との距離に応じたタイムラグがありながらも、おおむね2~3週間で沖縄県と同じようなカーブを描き、やがて次第にピークアウトしていくでしょう」(同)
要するにオミクロン株
宮崎県新興感染症医療コーディネーターの佐藤圭創氏によると、
「宮崎は今、ちょうど感染者数がピークを迎えています。例年の統計から予測すると、2週間後、関東なども含め全国的なピークに向かっていくと思われます。ピーク時の感染者は若い人が多く、感染症はよく動く若い層から広がります。そこから若い人の父母世代に、さらに高齢者にうつっていきます。1カ月前、宮崎では感染者に占めるニンバス株の率は半分くらいでしたが、今はニンバスとその関連株を含めるとほぼ100%になっています」
新変異株の“本州襲来”が間近に迫っているわけだが、
「ニンバスは正式には『NB.1.8.1』と呼ばれており、オミクロン株BA.2の亜型になります。ニンバスという呼称は、正式名称であるNB.1.8.1のNBから取ったものだと推測できます」
と、先の藤田医師。
「オミクロン株はBA.1から始まり、それがその亜型であるステルスオミクロンBA.2へと変異し、最終的にはBA.5にまで変異しました。つまり今回のニンバスは、2022年に感染拡大したBA.2にまで先祖返りしたものの亜型ということになります」
要するにオミクロン株の新たな主流、ということだ。
「ニンバスというと、突然新たなウイルスが来た、という感じがしますが、厳密にはオミクロン株の一種で、遺伝子変異が起こったためBAからNBに名称が変化したものの、その性質はほとんど変わっていないのです」(同)
「通常のかぜと同じような症状」
ニンバス感染者の診断・治療にあたってきた藤田医師はその“威力”をこう分析する。
「ニンバスは感染力の強いオミクロン株の、さらにそのまた変異株ということで、感染力はものすごく強い。ただその反面、患者さんの症状を見る限りでは弱毒化しているようです。私はこれまで、ニンバスに感染したと思われる患者さんを50人以上見てきましたが、多くは通常のかぜと同じような症状でした。喉の痛みを訴えているのは、ニンバスに感染した患者さん全体の3分の1に過ぎません」
メディアなどで強調される“カミソリを飲んだような喉の痛み”という症状については、
「私が見た限りでは、そのような症状を訴える患者さんは一人もいませんでした。これまでの診察の経験から自信を持って言えることですが、“カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”という報道は、実際の臨床とものすごく乖離しています。ニンバスの症状は軽いものであり、恐ろしく危険なウイルスである可能性は100%ありません」(同)
8月28日発売の「週刊新潮」では、治療薬の使用およびワクチン接種の「費用対効果」などを含め、複数の専門家の解説に基づき「ニンバスの真実」について4ページにわたって特集する。
「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載
マイコメント
どうもマスコミの報道に踊らされているようです。
マスコミと言うのはけっこうこういうパターンが多く、それを知った国民が
「そりゃ大変」と騒ぎだすのです。
もう少し冷静に観察してみている必要がありそうですね。

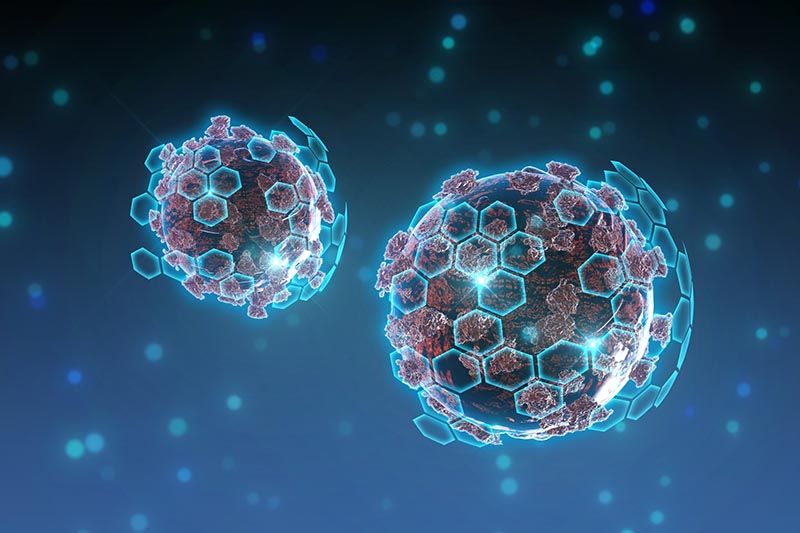



コメント